一昨日のNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、
山に生きる、山に教わる - 森林再生・湯浅 勲
まさしく、ここ北遠水窪の今と明日への課題を映し出していた
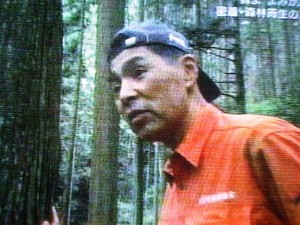
戦後に国内全域で植林された人工林(杉や檜)は、林業の衰退により荒れはて
間伐などの手入れもままならず放置され、日本中の森が死にかけている
山の荒廃は、環境悪化を招き、いずれ都会にも甚大な被害をもたらす
森を守る、、、いや森を再生し、蘇えさせることが急務となっている
湯浅氏は、地元の森林組合で、毎日荒れた山に入り森を再生させてきた
しかし、現場の苦悩と重なる難題は想像を絶することと思う
大半の森林組合や山林労働者は、未だに低賃金と不安定な雇用条件下にいる
山村の高齢化と過酷な労働環境は、若者たちからの林業離れを起こした
林業に関わる人の大半は、既に定年の歳をはるかに越えている

本気で社会が、地球温暖化や環境悪化を食い止め、CO2削減をしようとするなら
それは、生業(なりわい)となりえる森林、、、林業の再生以外にない
都会の人が取り組むエコ活動の、数千倍いや数億倍の効果を生む現実がある
(多くの人の環境への意識貢献には、価値があることはもちろんですが)
言葉は悪いが、きれいごとでは既に地球規模の環境破壊から身は守れない
まずは、山の現実を見たことが無い都会の人たちに、いまの森を知ってほしい
100年先の私達の未来をみすえて、、、
水窪さん お早うございます。
配管設計の仕事をやめて故郷に帰り、半分になった給料で頑張っているという湯浅氏ですが、彼の語り口には自信がみなぎっているように感じられ、救われた気持ちになりました。
町に住む自分として、環境負荷の低減で直接努力していることといえば、
①マイカー利用の自粛 ②家電製品待機電力のカット ③古新聞・古紙リサイクルの徹底 ④家庭ゴミ分別の徹底 ⑤スーパーでのレジ袋辞退 ⑥室内暖房温度の制限 くらいのものです。
観ましたよ。
頼もしい限りです、こんな人もいるのだと。
昨日のブログにも考えさせられました、力不足ですが私スタイルんで、水窪の良さをブログで発信し続けるのが今、できることかなと思います。
クライネマンさん こんばんわ
すみません、、、少し言葉が足りませんでした
都会の人たち、もちろん田舎の人もですが、一人ひとりの小さなエコ活動の理解と積み重ねが大切である事は間違いありません
ただ、国も地方自治体も環境保全といいながら、林業への支援に本腰を入れているとはいえません
湯浅さんのいるような組合は、ごくごくまれなのです
人材の育成や林業支援の体制を早急にしないと、本当に大変なことになるのだと思います
けいこさん こんばんわ
自分も何も出来ない状態で、とても偉そうなことを言える立場ではないのですが、、、
先輩の言われるように、ひとりひとりができることから、それぞれの形で水窪の町や森を考え、守らないといけないんじゃないかと思います
決して無理をする必要も無いのですが、ただ衰退していく町の姿、荒れていく森の姿を見て何もしない、、、それは、やはりいけないのではないかと・・・
自分の生まれ育った場所を愛することが出来なくなったら、それはとても悲しいことなのではないでしょうか
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
前の記事
次の記事
写真一覧をみる

 日記/一般| 天竜区|
日記/一般| 天竜区| 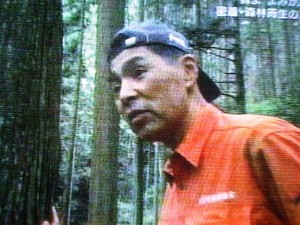

 at 2009年02月05日 20:25
at 2009年02月05日 20:25