今日は少し最近話題の農業のお話です。
一昨日もTVでTPP問題が話題になっていましたが・・・そのことについて!
ここからは私論です、チョッと長くなってすみません(異論も多々あるとおもいますが)
まずは、この問題を語る前に論点を整理しないといけないかと思います。いま農業現場の正確な実態の把握、これまでの農業政策などの問題点がごちゃ混ぜになり、一般の人の認識に随分誤解をあたえているように思います。
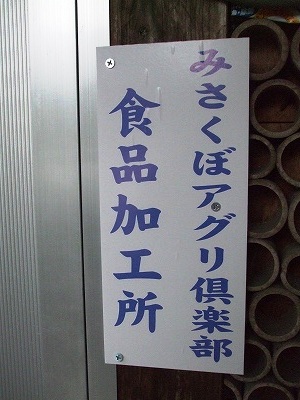
日本農業の正確な実態と食料自給率の関係はというと・・・まず、皆さんが思い違いしているのは、日本農業生産額は世界第5位であり押しも押されぬ農業大国だということです。更に農水省のいう自給率はカロリーベース数値であるため、自国生産量及び輸入量での誤差が生じています。この自給率には毎日廃棄される食物や自家生産分はカウントされませんし、農家の直売品、国内飼育された畜産でも外国産飼料を与えたものは国産扱いではありません。大規模畜産農家において生産した食肉はその時点でカウントされないという大きな矛盾まであります。それらをカウントすると生産ベースでいまでも実際の自給率数値は50%をはるかに超えると思います。現実に畑で放棄される農産物や規格外の品(これらもカウント外ですが)は未だに大量にのぼりますし、私達のお茶をはじめコメも必要以上の備蓄や在庫がされ農産物価格の低下に拍車をかけていますし、国内食料は異常なくらい有り余っています。足らずは穀物類なのですが、しかし、国内業者が輸入品を多用するのは国産の品質が劣り使えないという事情にもよります。品質の向上により国内産消費も生産も数値が上がる余地はあります。将来の自給率予測(これも専業経営農家の著しい生産伸び率は公表していません)はともかく、現状では政府の発表する数値や内容はかなり歪曲されていることも事実です。この数字のまやかしには、肥大化したJAの都合(農家における中間所得層の囲い込みや独占市場の確保)や農水省の既得権益のための嘘が隠れていることも承知しないといけません。むやみに消費者の不安をあおるようなマスコミや国の情報操作には時々憤りを感じます。推測するに日本農業があくまで弱い立場を強調しないと国の農水関係予算と仕事はなくなってしまうのではないかと。
それと高齢化による農業者人口の減少による生産量の衰退を心配しますが、現実にはこの事由による農作物生産量減少(耕作の放棄地は確かにしていますが)は微々たる物で、今では国内農産物総生産量の7割は1割の農業法人や大規模農家によります。加えて1ヘクタール未満の8割の兼業農家の農業所得は農家の生活に影響を与えるほどの数字ではありません。コメですと概算金額で年間所得20万円ほどでしょうか?例えば、市役所に通う兼業農家がコメの値段に生活レベルを左右されることはほぼありません。また、100ヘクタールを越え年商1億以上の売上を挙げる農家には十分外国産との競争力の余地があります。高齢化による農業放棄地の増加、農家件数の減少と生産額減少を同一の土俵で語るのはどうか?であり、全く異質の問題です。農業放棄地の環境への影響や国土保全との関係については、また改めるとして・・・。あえて問題となるとすれば、それなり(これがあいまい)の規模で農業を営むものたち、大規模ではない専業農家、いうなれば私達のような立場で農業生計をたてている全体の1割の存在の処遇なのです。大規模経営に参画し農家同士の経営統合を図るのか?新たな集落農業の道を選択するのか?また別の事業に生計の糧をもとめるのか?いわゆる付加価値農業・6次産業化農業への参入ですが、ここをどう対処するかは、一番難しい問題かもしれません。
ともあれ、当面の課題は現状にそくさない農業政策と立ち遅れた現状農家の経営システムと雇用体制です。将来的に国として(今の日本の無能な外交政策では)TPPなど自由貿易は避けて通れないでしょう。また、そうでなくても、日本農業の国際競争力の強化や若者の農業雇用進出など近未来の農業設計を考えるには過渡期なのかもしれません。更に一歩踏み込めば戦後JAの部分的解体や農水省改革も必要かもしれません。
次に、政策の課題としては、まずは地域・農業規模・農家ごとになすべきことの方向づけを厳格にすることであり、それには農業形態としてのマクロ農業とミクロ農業の選別と区分けをすることが必要かと考えます。マクロ農業の確立のためには、効率的な平地での大規模農業推進のための技術支援や大規模農家間の更なる統合・経営強化が急がれますし、安定した食料自給生産のための、意欲ある農家への経営規模拡大のための安定化支援と助成、農地の流動化を推進することです。更には助成金ばら撒きをやめた兼業農家の集約と組織改革といった政策指導も必要です。ミクロ農業で言えば、中山間地における農業に採算効率を求めることは難しい、、、ならば中山間地農業の及ぼす多面的多機能的価値を認め文化農業、環境農業として小さな農業を守ることをコンセプトとし、新たな環境税などを財源とした環境政策の支援・実施をするのだということをはっきり国民に説明し理解を得ることが大事だと考えます。
いずれにおいても、今後は中長期における農業ビジョンを明確にした段階的な政策に取り組むことが欠かせません。農政の蛇行や寄り道は農家にとっても国民にとっても悲劇以外何ものでもありません。これを機に戦後農業政策の誤りを国も農家も認め、真摯に現状に向き合わないといけないと思います。ここで誤解してほしくないのは、けっして現段階で自由化を推進すればいいというものではないということ。ビジョンなきご都合主義の政策の急激な転換は混乱と現状農家の生活環境を悪化するだけですから。私自身、その点では大きな不安を抱いているのも正直なところです。ただ、肝心なことは、今後のしっかりとした農業構築のビジョンを持った上での数年かけた段階的な農業改革や政策が、日本農業の体質を強くするということであり、次世代を託す若者へつながるということです。いつまでも日本農業を弱者化していても、若者農業者達の将来に希望はありません。時代の変化に惑わされず、農家それぞれが自立の理念を持つことが大事ではないでしょうか。また、続きは後ほど・・・
ここまで読んでいただいた方へ・・・
まとまらない話に長々とお付き合いいただいてすみませんでした

 日記/一般| 天竜区|
日記/一般| 天竜区| 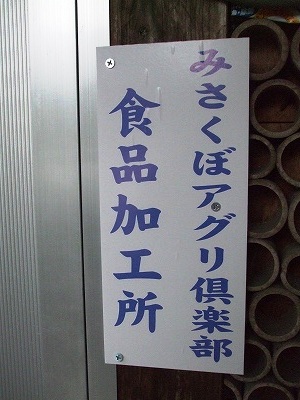
 at 2010年12月24日 08:48
at 2010年12月24日 08:48